Recruit site
-
トップページ
TOP
-
当社について
ABOUT US
-
仕事について
ABOUT JOB
-
働く環境について
WORK STYLE
-
採用情報
RECRUIT

技術部 レンズ設計グループ 開発レンズ設計課
2023年入社
数理物質科学研究科 電子・物理工学専攻 修了
私は学生の頃に網膜剥離を患い、光を扱う医療機器に失明の危機を救われたことがあります。この経験があり、今度は自分が患者を救う側になりたいと切望して医療機器業界を目指しました。研究室ではレーザーを扱っていたため、その専門性に関連する医療機器として、コンタクトレンズにたどり着きました。コンタクトレンズは世の中に広く普及しており、医療機関に設置される検眼機器や手術機器などと比べ、遥かに多くの患者の目に貢献できる点が独自の強みだと考えました。
その中でもシードを選択したきっかけは、「製品の多様性」や「国内最大の度数範囲」といった特徴です。この環境で、世界中の多くの人の目を救いたいと考え、シードを選びました。

私の部署は、新規レンズの開発から量産化までを担うグループで、主に「レンズデザイン設計」「試作製造」「解析と評価方法の確立」に注力しています。その中で私が担当するレンズデザイン設計では、光学理論に基づきレンズ形状の設計値を数十㎛単位で定め、CADを用いてレンズの図面を作成します。
新しい光学デザインや新素材を取り入れたレンズを製品化する際には、装用試験や承認申請試験を経る必要があります。それらの試験に出すレンズは、厚生労働省の規格(度数、直径など)を満たす必要がありますが、試作段階では規格外のレンズが出来上がることも多々あります。そこで、フィードバックを活かして再設計を繰り返し、最終的に狙い通りのスペックを持つレンズを設計することが私のミッションです。
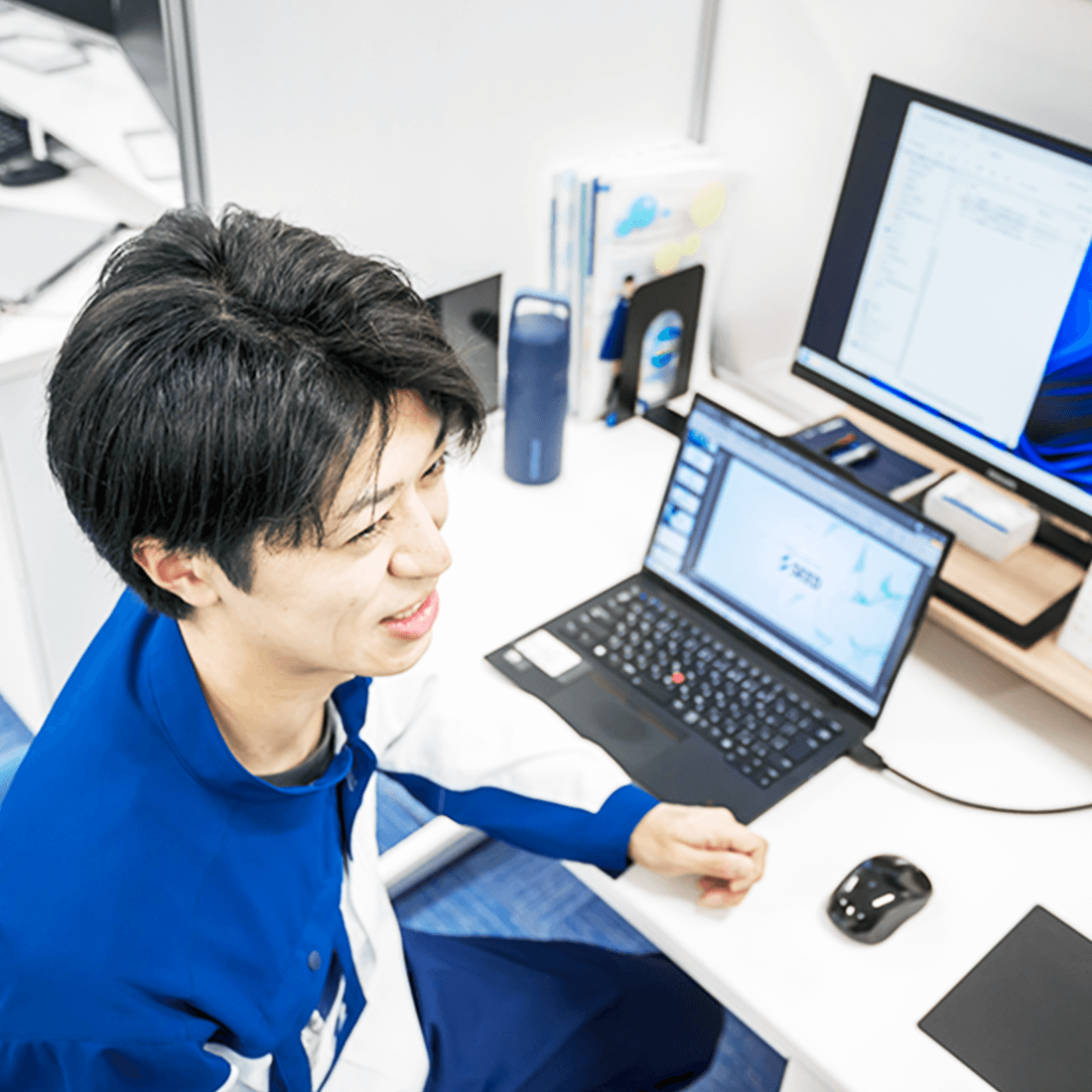
レンズ設計業務は、コンタクトレンズ製造フローの最上流工程です。レンズが狙いの度数を発揮するか否かは、光学設計部分に託されています。また、レンズを一つ作るにも、設計完了から最短でも数日を要し、一朝一夕では完成しません。時間と労力と材料を費やした結果、規格に満たないレンズができてしまったら、再設計を余儀なくされてしまいます。開発スケジュールに響いてくる可能性もあるため、そのような手戻りを極力生まないよう、慎重に設計値を定め、描き損じの無いように図面を作製する意識のもと、業務に取り組んでいます。
だからこそ、要求された度数のレンズが作製できたとの報告があった際は、大きな喜びと安堵を噛み締めています。

近年注目されている近視進行抑制分野を、さらに活性化するようなレンズデザイン設計をしたいです。私は小学生のころから目が悪く、裸眼で過ごせる人を羨ましく感じてきました。社会のデジタル化にともない、近視人口が急増しています。自分が開発に携わった近視進行抑制レンズの恩恵を、私の子供世代や孫世代が受け、未来の子供たちが視力に何不自由なく暮らせる日常が訪れることがあれば、レンズ設計者冥利に尽きると考えています。
幸い、学会やセミナーへの参加に意欲的な先輩が多いため、学ぶ機会に非常に恵まれた環境です。日々の業務に取り組みつつ、学会等へ参加することで、理想を現実とするために必要な最新の知見を学んでいきたいです。
1日の仕事の流れ
- 9:00
- 出社
メール・Web掲示板・予定を確認し、この日の進捗会議の資料を作成する。
※フレックス制度を利用し、早い時間に出社することもある。 - 10:00
- 開発品の進捗会議
携わっている開発品に関して、各部署のプロジェクトメンバーが一堂に会した場で、技術部としての進捗やスケジュール状況を話し合う。 - 11:00
- 課題について議論
狙いの光学性能が発揮されなかったり、レンズ形状不良等、開発品の課題について議論する。上司・先輩と議論して解決の糸口を探し、次のアクションを定める。 - 13:00
- 昼礼・昼食
部内の昼礼後、食堂で同期と食事する。 - 14:00
- 開発品のレンズ設計
要望された度数の試作レンズを設計する。 設計数値を定め、それを元にCADで設計図面を描く。 - 17:00
- レンズ金型の加工準備
別チームに、レンズ金型の加工依頼。
加工に必要な図面データを揃え、指図書(数量や納期などの情報が記載された書類)を提出する。 - 18:00
- 退社
その日の業務内容を記録し、帰宅する。

